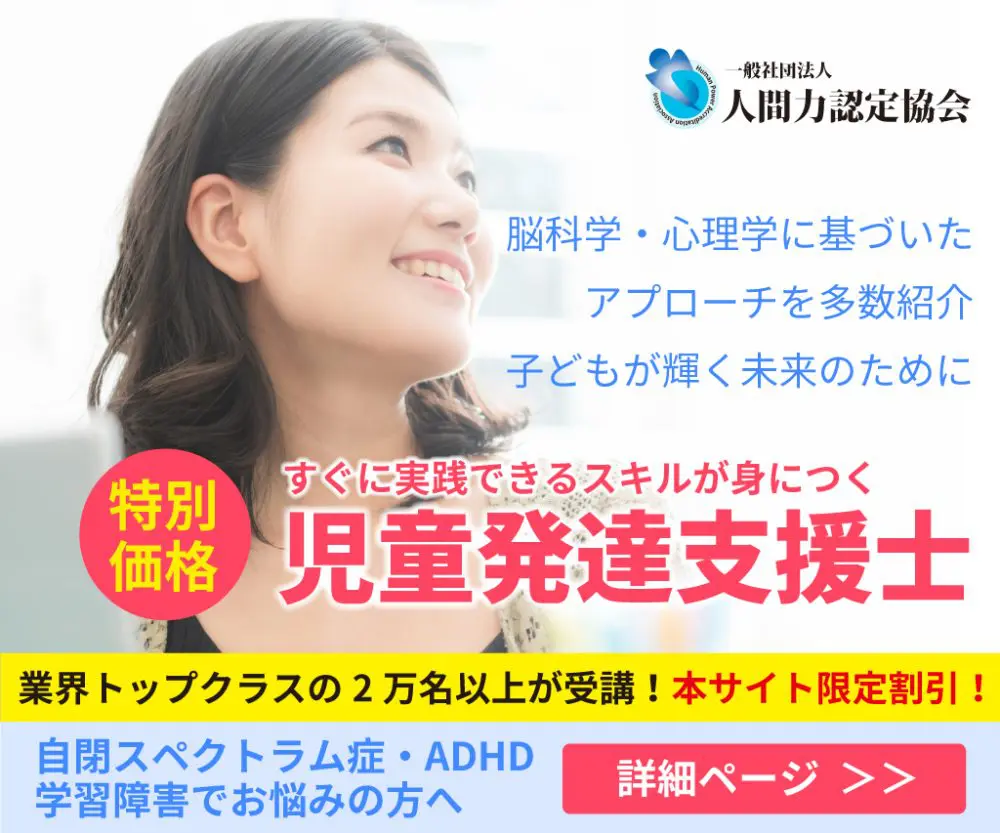社会の変化や、ライフスタイルの変化、新たな病気の流行など様々な事がきっかけとなり、日々精神疾患の方は増え続けていると様々なニュースやメディアで報道されています。
ですが、実際にどの精神疾患が多くて、どの精神疾患は少ないのかまでは分からない方が多いのではないでしょうか?なんとなくよく聞く病気は多そうだけど・・・なんて方も少なくないでしょう。
今回は、2024年12月時点で厚生労働省などから発表されている情報を交えて紹介をしていきたいと思います。
日本国内の精神疾患の現状について
まず日本国内の精神疾患の統計から見ていきましょう。精神疾患を有する総患者数の推移は令和2年度時点で約614.8万人で、そのうち入院患者数は約28.8万人、外来患者数は約586.1万人となっています。
また、気分障害(躁うつ病を含む)が169.3万人と一番多く、次に神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害が123.7万人、そして統合失調症型障害及び妄想性障害が73.7万人となっています。
気分障害は、うつ状態のみが認められる時はうつ病、うつ状態と躁状態を繰り返す場合は双極性障害(躁うつ病)とされています。よく聞く精神疾患ではないでしょうか?
次に神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害ですが、こう聞くと聞き覚えのない方が多いと思います。神経症性障害は、ノイローゼや神経症と呼ばれていたものです。社会不安障害、パニック障害、全般性不安障害、強迫性障害などがここに含まれることがあります。ただし、専門書などで細かく分類すると変わることもありますのでお気を付けください。
ストレス関連障害は、文字通りストレスによって身体に影響を与えるものを指します。意欲の低下であったり、いつまでもイライラしてしまう、不安が取れない、頭痛や肩こり、胃痛、動悸、息切れなどが症状として挙げられます。適応障害やパニック障害、PTSDなどが分類されます。
身体表現性障害は、自覚できる身体症状があっても、検査や診断では明らかに身体疾患は認められず、何らかの薬物の影響なども認められずに、不安や悩みなどを抱え続けているのが特徴です。症状や原因が様々で、症状などに合わせて治療などが行われていきます。
外部リンク
参考:厚生労働省 精神保健医療福祉の現状等について
世界で見る精神疾患の数とは?
WHOから出ている以下の統計によると、世界では約2億8千万人がうつ病を患っているとあります。また、15歳~29歳の死亡原因の第4位ともなっています。
外部リンク
参考:WHO Depressive disorder
※リンク先は海外のサイトとなっています
その他にも統合失調症は約2000万人、双極性障害は約4000万人以上だと言われています。そしてこの増加傾向はしばらく続くという推計もあり、国を問わずに精神疾患への対策、メンタルヘルス(こころの健康)を守ることが急務だとされています。
世界から見る日本の精神病床数は?
日本の精神病床数は、令和2年の時点で約32.4万床となっています。
これは多いのか少ないのか分かり辛いと思いますので、2021年に日本医師会から出ている総病床数の国際比較を見ていきましょう。
外部リンク
参考:公益社団法人 日本医師会 病床数の国際比較(2021年)
ドイツが106,176床、アメリカが82,489床、フランスが55,377床、イギリスが23,658床となっており、日本が一番多いのが分かるかと思います。ですが、ここで注意していただきたいのは、精神病床だけが多いのではなく、他の病床数についても多いということを覚えておきましょう。
何故ここまで精神病床が多いのでしょうか?その理由の1つには、精神疾患を持つ方への偏見や誤解、差別などが強く、地域によるケアが行いづらく、病院に入院せざるを得ないという面があります。
年々こういった偏見や差別は減っている傾向にはあります。ですが、どうしても無くならないというのが悲しい現実でもあります。
また、本人やその家族が精神疾患をある事を恥ずかしい、他者に言えない、相談し辛いといった考えも影響しています。精神疾患は誰でもかかる可能性のある病気で、決して恥ずかしいことではありません。
それでも、そういった差別の目で見られる恐怖、自分が弱いからうつ病などになってしまったという誤解からの自責の念、家族が精神疾患だと言えないという気持ちなどから入院に頼り、その結果病床数が増えていったのは1つの理由でしょう。
日本のメンタルヘルスにおける歴史とは?
日本における精神障害者に関しての初めての法律は1900年にできた精神病者監護法だと言われています。とはいっても、欠点の多い法律でもあり、当時すでに理解が進みつつある諸外国に比べて環境が悪かったようです。1919年に精神病院法が出来たり、1950年に精神衛生法が作られました。
その後、1987年に精神衛生法が精神保健法へ改正があったり、様々な事件がおきて制度の改定があり、1995年に精神保健法を精神保健福祉法へ改正されました。
海外と比べるとメンタルヘルスへの取り組みが遅れているという事実もあります。この理由にも、精神障害者に対する偏見が強いことや、精神疾患が恥ずかしい、我慢すべきことだと捉えてしまう日本人特有の性質が挙げられます。
悩みやストレスを根性でどうにかするなんて考えを、いまだに聞くことは少なくありません。精神疾患は根性ではどうにもなりません。1つの病気です。そんな事をしていると重症化して、回復までの時間がかかり更に悪い方向へと進む可能性もあります。
自分で自分のメンタルヘルスを守ろう!
皆さんは自分のメンタルヘルスの守り方はご存知でしょうか?このブログでも何度も紹介しているため、他の記事をご覧になって知っている方もいるでしょう。ですが、改めて確認の意味も込めて見ていきましょう!
生活習慣の改善
なるべく規則正しい生活習慣をこころがけましょう。早寝早起きをして睡眠時間を確保することで、疲れの解消などにも繋がります。睡眠時間が足りないと不安や抑うつが強くなり、うつ病にかかりやすいとの研究もあります。
栄養が取れるバランスの良い食事や適度に身体を動かすことで、身体的な健康を維持することも大切です。身体的健康と精神的健康はお互いに作用し合います。
セルフケアをする
まずは自分自身のことを深く理解することが大切です。自分がリラックスできる時間、ストレス解消ができる物事、ストレスのたまる瞬間、ストレスで限界を迎えた時に現れる身体や心のサインなどを知っていきましょう。
これらを知ることで、メンタルヘルスのセルフケアを行うことができます。ストレスが溜まりすぎる前にストレス発散をしたり、精神疾患へと繋がる前に相談をしたりと様々な手段を取れるようになります。
相談できる相手を見つける
これは身近な方、例えば親友や家族、同僚や上司など様々な方がいます。その中で自分が信頼して相談できる相手はいますか?もしいなければ、保健所や保健センター、精神保健福祉センター、医療機関や専門家などを頼っても問題ありません。普段の自分を知らないからこそ、言いやすいという方もいます。
相談できることで、心の中で溜まっていた悩みや不安などを軽減し、自分だけでは見つからなかった解決策を一緒に探していくことができます。1人で悩みや不安に押しつぶされる前に、是非相談してみてください。
メンタル系の資格を学習する
メンタル系の資格というものは沢山存在しています。国家資格から民間資格、通信講座で気軽に取得できる資格まで様々です。
- 公認心理師(国家資格)
- 精神保健福祉士(国家資格)
- 臨床心理士
- 産業カウンセラー
- メンタルヘルス・マネジメント検定
- メンタル心理カウンセラー
- メンタルヘルス支援士
このようなものがあります。国家資格は学歴や経歴が求められますが、民間資格の一部に関しては、どなたでも受講できるようになっているので、初めて勉強するという方でも安心です。初心者向けの資格としてどのようなものがお勧めか照会している記事がありますので下記をご確認ください。
関連記事
【2025年版】メンタルヘルスに関する初心者向けお勧め資格3選!
メンタルケアができる資格:メンタルヘルス支援士とは
最後に今注目されている資格「メンタルヘルス支援士」についてご紹介いたします。
メンタルヘルス支援士は一般社団法人 人間力認定協会が認定する民間資格となります。
人間力認定協会は発達障害支援の代表的資格でもある「児童発達支援士」を認定している団体であるため、信頼性は十分にあると言えるでしょう。弊社でも児童発達支援士のノウハウの一部を導入しています。児童発達支援士などの発達障害関連資格の累計受講者数は4万名を超えているようです。(2025.2現在)
メンタルヘルス支援士は発達障害関連の資格というわけではなく、その名の通り「メンタルヘルス(心の健康)」を向上させることを目的とした資格となっています。メンタルヘルス支援士講座で学べる内容は、以下のようになっています。
- 精神疾患に関する基礎知識
- 発達障害と精神疾患・依存症の関係性
- 認知行動療法の種類と基礎知識
- カウンセリングの基本姿勢
- カウンセリングに役立つ心理学テクニック

この資格に内容や難易度が類似する資格としては、キャリカレの「メンタル心理カウンセラー」があげられます。その際の違いという点では、発達障害やその二次障害との関連性を学べる点と言えるでしょう。発達障害の専門資格を扱っているだけあり、そこは強みの一つのようです。
またメンタルヘルス支援士は「DSM-5TR」に基づいた表記がされていることも特徴の1つです。DSMというのは、アメリカ精神医学会が発刊している医学書のことですが、2022年に最新版となる「DSM-5-TR」が発刊されました。それまでは2013年に発刊された「DSM-5」という医学書がベースとなっていました。およそ9年ぶりに情報が更新されたのですが、その最新情報に対応している資格だということです。精神疾患や発達障害関連の研究は現在も進んでいるため、学ぶのであれば新しい情報であるにこしたことはないでしょう。DSM-5-TRでは、より差別感のでない表現や理解しやすい表現が重視されているので、受講する際にも気持ちよく学ぶことができるのかもしれません。興味のある方は下記より特設サイトをご覧ください。
[メンタルケア資格]メンタルヘルス支援士の内容や試験概要をご紹介
【まとめ】精神疾患は本当に増えている?最新データを交えて紹介!
今回は現在公開されている最新のデータを交えつつ、精神疾患についての紹介をしてきました。この記事は、最新の統計データなどが公開されるたびに更新していきたいと思います。
増加傾向にある精神疾患、そこから自分や周囲の方を守るためにはどうすれば良いのか、自分だけは大丈夫なんて考えではいざメンタルヘルスの不調になった時に気付くのが遅れてしまうかもしれません。日々、メンタルヘルスに気を付けて過ごしていきましょう。
メンタルヘルス支援士のお申込みはこちらから。人気のメンタルケア・心理カウンセラー関連の資格。精神疾患の種類や特徴を理解し…